サイバーセキュリティ対策に欠かせない自社のリスク把握について
サイバー攻撃の被害が増してきている中、サイバーセキュリティ対策への取り組みは企業にとって重要な要素の1つです。今回の記事では、サイバーセキュリティのリスクとなりえる要素を解説します。

目次
サイバーセキュリティとは
サイバーセキュリティとは、コンピューターシステムやネットワークインフラ、デジタルデータなどの情報資産を、日々進化するサイバー攻撃から守ることを目的としています。
近年、サイバー攻撃の手法は巧妙化しており、フィッシング詐欺やランサムウェア、標的型攻撃など、多様な脅威が企業や組織を狙っています。令和5年には、サイバー犯罪による被害総額が80億円を超え、その深刻さが浮き彫りになりました。
サイバー攻撃を受けた場合の影響は甚大です。顧客の個人情報や企業の機密データが流出するリスクがあり、さらにシステムダウンによるサービス停止は、事業継続に重大な影響を与えかねません。
企業にとってサイバーセキュリティ対策は、もはや選択肢ではなく必須の経営課題です。
サイバーセキュリティのリスク

サイバーセキュリティのリスクとして、次の内容を解説します。
- サイバー攻撃
- システムやサーバーの不具合
- ヒューマンエラー
- 災害発生
それぞれのリスクを詳しくみていきましょう。
サイバー攻撃
サイバーセキュリティとして、最も注意すべきはサイバー攻撃です。主な攻撃手法を下記に挙げます。
|
攻撃手法 |
特徴 |
|---|---|
|
マルウェア |
トロイの木馬やスパイウェアなど、相手の端末に侵入し被害を及ぼす。近年はランサムウェアの被害が増してきている |
|
フィッシング詐欺 |
実在のWebサイトを模倣した偽サイトに誘導し、重要な情報を盗み出す |
|
SQLインジェクション |
不正なSQL文を送信し、データベースの改ざんなどを行うサイバー攻撃 |
|
DoS・DDoS攻撃 |
標的となるサーバーに過剰なデータ送信を行いシステムを過負荷状態にする |
|
中間者攻撃 |
通信間に第三者が割り込み、不正に傍受する |
|
内部脅威 |
アクセス権を付与された者が悪用し、システムに不利益をもたらす |
攻撃が巧妙化してきているため、常に最新の情報に注意する必要があるでしょう。
システムやサーバーの不具合
システムやサーバーの不具合は、サイバーセキュリティの重大なリスク要因です。ソフトウェアの更新管理の遅れに気を付けなければなりません。セキュリティパッチの適用が遅れることで、既知の脆弱性が修正されないまま放置され、攻撃者に付け入る隙を与えてしまいます。
このような不具合は、マルウェアの感染を招く可能性が高く、一度感染すると社内ネットワーク全体に被害が広がる恐れがあります。定期的なセキュリティアップデート、設定の見直しが必要です。
ヒューマンエラー
ヒューマンエラーの例として、従業員が会社に無断で個人のデバイスやクラウドサービスを使用するシャドーITや、意図的な内部不正、単純なミスなどが挙げられます。人為的なミスが要因で、重要なデータが漏洩したりシステム障害が発生したりと、大きな問題になりかねません。
特に注意すべきは、従業員の単純なミスや誤解から生じるセキュリティ侵害です。メールの誤送信やパスワードの使い回し、不審なリンクのクリックなどの基本的なミスが、データ漏洩やシステムへの不正アクセスを引き起こし、企業の評判や顧客からの信頼を大きく損なう可能性があります。
災害発生
データセンターやサーバーが社内にある場合、自然災害によるサイバーセキュリティリスクは特に深刻です。地震や洪水、火災などの大規模災害が発生した場合、物理的な設備の損壊やネットワークの切断により、システムの復旧が極めて困難になるでしょう。
自社設備が機能を停止してしまうと、重要なデータへのアクセスが不可能となり、業務システムも完全に停止します。事業継続に致命的な影響を及ぼし、顧客へのサービス提供も停止となりかねません。
災害発生のリスクに対しては、クラウドサービスの活用やバックアップセンターの確保など、事業継続計画の一環として対策を講じることが重要です。
被害にあう企業の傾向

サイバー攻撃の最近の傾向として、攻撃者が中小企業を踏み台として利用するケースが増加しています。中小企業は予算や人材の制約からセキュリティ対策が十分でないことがあるため、攻撃者の標的となる場合があります。
大手企業のサプライチェーンを狙った攻撃もありました。セキュリティ対策が比較的脆弱な下請け企業のシステムに先ずランサムウェアを感染させ、そこを起点として取引先である大手企業のネットワークへ侵入を試みた事例となります。
この際、下請け企業のシステムから侵入したランサムウェアが、大手企業の基幹システムにまで到達し、工場の操業停止や重要データの暗号化など、深刻な被害をもたらしました。
リスクへの備え方

経済産業省からは、サイバーセキュリティ経営ガイドラインとしてリスクへの備え方が公開されています。
公開されている内容は次の通りです。
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|---|---|---|
|
経営者がリーダーシップをとったセキュリティ対策の推進 |
サイバーセキュリティリスクの管理体制構築 |
サイバーセキュリティリスクの認識、組織全体での対応方針の策定 |
|
サイバーセキュリティリスク管理体制の構築 |
||
|
サイバーセキュリティ対策のための資源(予算、人材等)確保 |
||
|
サイバーセキュリティリスクの特定と対策の実装 |
サイバーセキュリティリスクの把握とリスク対応に関する計画の策定 |
|
|
サイバーセキュリティリスクに対応するための仕組みの構築 |
||
|
サイバーセキュリティ対策における PDCA サイクルの実施 |
||
|
インシデント発生に備えた体制構築 |
インシデント発生時の緊急対応体制の整備 |
|
|
インシデントによる被害に備えた復旧体制の整備 |
||
|
サプライチェーンセキュリティ対策の推進 |
ビジネスパートナーや委託先等を含めたサプライチェーン全体の対策及び状況把握 |
|
|
ステークホルダーを含めた関係者とのコミュニケーションの推進 |
情報共有活動への参加を通じた攻撃情報の入手とその有効活用及び提供 |
|
まとめ
今回の記事では、サイバーセキュリティの解説をしました。サイバーセキュリティとは、コンピューターシステムやネットワークインフラ、デジタルデータなどの情報資産を、日々進化するサイバー攻撃から守ることを目的としています。
企業にとってサイバーセキュリティ対策は、もはや選択肢ではなく必須の経営課題です。大手企業に対する踏み台として中小企業が攻撃対象となることも少なくありません。
その中でも、ID管理を強化することは、サイバーセキュリティの基盤を支える重要な要素です。IDaaSを活用することで、ID管理の一元化や認証プロセスの強化を実現できます。
サイバー攻撃から自社の情報資産を守るために、IDaaSの導入をはじめとした総合的なセキュリティ対策への取り組みがより重要となっていくでしょう。


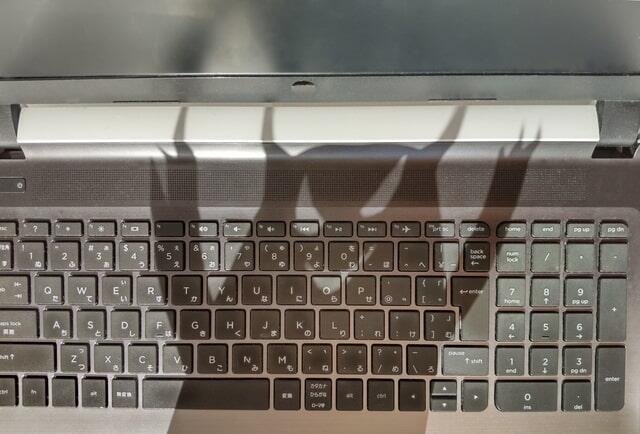


 無料デモ依頼
無料デモ依頼 資料ダウンロード
資料ダウンロード